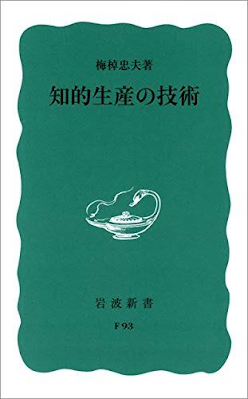部屋の掃除をすることがありました。
部屋の掃除と本棚改造を実行中です
— 尼野ゆたか@5月15日コラボ小説刊行! (@amano_yutaka) October 6, 2023
最低限の目標だった本の整理がこなせたので、とりあえず成功の札を貼っています。
成功か失敗かで部屋の掃除を評価するってどないやねんという感じですが、今回は今までにない取り組みを行いましたもので。
どんな取り組みかというと、岩波新書を参考にお部屋掃除にイノベーションを創出したのです。ほんまかいな。
「知的」「生産」「技術」
その本がこちら。梅棹忠夫「知的生産の技術」です。全身これパワーワードみたいなタイトルですね。
1969年刊行。僕の手元にあるのは2016年5月の第96刷です。96刷!
筆者は梅棹忠夫。京大式カード作った人ですね。専門は民族学(Not俗)。
「昭和の知の巨人」、って感じかなあ。実家にも「モゴール族探検記」がありました。回収してきたのでまた読もうと思っております。
さて内容ですが、言ってみればタイトル通りの感じです。今でも同種の名前の新刊がビシバシ出版されることからすると、先駆者的一冊とも言えましょうか。
「追加さしこみ自由自在の、いわゆるルース・リーフ式のノートのほうが便利だ、ということになる」
「現在のようにスチール・キャビネットなどなかったころだから」
ルーズリーフのくだりとかほんとびっくりしました。これ、「まだ広く普及していない、やや珍しいもの」を説明する時の文章ですよね。
まあ、1969年って半世紀前ですからね。黒い霧事件とか佐藤栄作訪米とか、ビートルズがアビーロード出したとかアポロ11号が月に行ったとかそういう年です。もはや歴史。
そんな「僕らが生まれてくるずっとずっと前」の本に一体なんの影響を受けたのか、読まれている方は疑問に思われることでしょう。体系的にスチール・キャビネットを追加差し込み式で使うようにでもなったのかみたいな。
しかし、古い本だからといって内容まで古びているわけではありません。考え方の土台の部分に説得力が宿っていれば、いつの時代でも通じるような普遍的な真理を掴んでいれば、読む者に新鮮な発見をもたらす事ができます。「街がまだジャングルだった頃から変わらない」ものは、確かに存在するのですから。
「なにがいったい、現代の知識人としての必要最小限の技能であるか」
いくつか例を挙げてみましょう。
たとえばこの本では、メモをすることの意義について、
「カードにかくのは、そのことをわすれるためである。わすれてもかまわないように、カードにかくのである」(漢字のトジヒラキは原文ママ)
と説明されています。
これはおそらく一つの真理であり、色々な人が色々な表現で、最近なら色々なエビデンスに基づいて、何度も何度も言ってきたことでしょう。
つまり内容としては陳腐すれすれなわけですが、しかし言葉のシンプルさと明瞭さ、そして読んでいて登場するタイミングの的確さによって、実に説得力を感じられるようになっています。
「こつこつと、文字で論理をくみたててゆくよりも、そらでかんがえたほうが、直観的な透察がよくきいて、思想の脈絡がはるかにうまくつくからである」(トジヒラキ以下略)
こちらも深く頷かされるところでした。
僕は小説を書く時、細部まで逐一プロットを立てていくより塊で浮かんできたものをそのまま書く方がしばしば早いし、(なにかと粗くとも)己にとっての本質を摑んだ形にできることがよくあります。作家の中にも似た感じの人は結構いらっしゃって、直接そういうお話を伺うこともあります。
そういう同輩には、大変納得がいく文章ではないでしょうか。僕はすっかり感心させられてしまいました。あの時の感覚を、こういう風に言語化できるもんなんだなあ。
さて。例示はこのくらいにして、そろそろ整理の話に入りましょう。
ずばり「整理と事務」という章がこの本にはありまして、そこでは「整理と整頓は違う」という話がされています。
「整理というのは、ちらばっているものを目ざわりにならないように、きれいにかたづけることではない。それはむしろ整頓というべきであろう。ものごとがよく整理されているというのは、みた目にはともかく、必要なものが必要なときにすぐとりだせるようになっている、ということだとおもう」
僕にとっては、まさしく目から鱗が落ちる一文でした。
生来片付けや掃除美化が下手で、苦手意識と恥ずかしく思う気持ちとが強く、取り組むには多大な精神的エネルギーが必要でした。
そのため、マズいほど散らかっても中々片付けられず、逆に一度やり始めると「ちゃんとせねば」「綺麗にせねば」というプレッシャーに追い立てられ、死に物狂いになってしまい余計に消耗してしまう……という、大変非合理的なプロセスを繰り返してばかりいました。
そんな僕なので、「きれいにかたづけることではない」という一言が、福音の如く響いたのです。
下手でも苦手でもいいわけです。「整理は、機能の秩序であり、整頓は、形式の秩序の問題である」。自分にとって必要な機能を実現できれば、その時点で整理は成功です。「美しいかどうか」という形式の部分は、ひとまず閑却してしまって構わないのです。これなら、できるかもしれない……!!
加えてこの考え方は、モチベーション管理のヒントも与えてくれました。
掃除や片付けに対して「汚くなった部屋を汚くない状態に戻そう」という姿勢で取り組むと、マイナスをゼロに戻すだけの無味乾燥な作業になりがちです。そこには創造性が伴わず、そもそも楽しみが生じにくいです。
しかし、「自分にとって使いやすくする」という形であると、より便利にしようという「工夫」や、どういう状態が一番便利だろうという「探求」が生まれます。どちらも大変創造的な営みですね。
カスタマイズと言い換えてもいいでしょう。自動車やバイクを例に挙げるまでもなく、カスタマイズは娯楽です。娯楽とは楽しいものです。片付けを楽しむための手段を、僕は遂に見つけ出したのです。わーい。
適切なゴールを設定しよう(意識高い系尼野ゆたか)
気づきを得てモチベーションが向上し、意識も高くなった尼野ゆたかですが、調子に乗ってそのまま掃除を始めたら失敗に終わることは間違いありません。
何しろ掃除の技術やセンスは一切向上しておらず、上がっているのは気分だけです。「掃除ができない尼野ゆたか」が「掃除に積極的に取り組めそうな気がしてきた尼野ゆたか」になっただけで、実務的な面での進歩は一切ありません。よって、ゴールはあくまで達成可能な地点に設定する必要があります。
しばらく考えて、今回の掃除のゴールは「本を『整理』すること」という一点に絞りました。
その理由は二つ。
一つは、部屋を構成する要素の中で最も深刻な無秩序に陥っていたのが本だということでした。
一度などは、何がどこにあるのか分からず同じ本を買い直すという悲劇を、身を以て体験する羽目に陥ることさえありました。
日々隙間時間に片付け。今日は必要な時に見つけられず仕方なく買い直した本が出てきました(ちくま学芸文庫『戦争における「人殺し」の心理学』)。
— 尼野ゆたか@5月15日コラボ小説刊行! (@amano_yutaka) January 5, 2022
二冊あってもなあ……面白い本ですが、どちらもあまり保存状態はよくないので(買い直した方も「可」かどうか)あげるのもはばかられます。とほほ
こんな思いはもう二度としたくない。持ってる本をもう一度うっかり買ってしまうよりもつらい。
もう一つは、本を片付けることについての具体的なヒントをこの本からいくつも見つけられたことです。
掃除の技術はなくとも、マニュアルはあるわけです。機械が苦手なうちの母親でも、説明書を見ながらであればBlu-rayレコーダーを操作し堂本剛が出演するテレビ番組を録画することができます。マニュアルさえあれば、尼野ゆたかが本をしっかり整理することも夢物語ではない!
まあ実際あの書斎には憧れる
どんなヒントを得たか。
まずは、整理するにあたって則るべき原則です。
「それぞれのものの『あり場所」が決定されている」ことを、本書では整理されている状態と定義します。「整理の第一原則は、ものの『おき場所』をきめる、ということである」。
本で言うなら、どんな本をどのスペースに配置するか、それをしっかりと決めるわけですね。
マイ・フェア・レディのヒギンズ教授の書斎みたいな馬鹿でかいスペースが用意できるわけではないので、どうしてもあちこちに本を散らして並べる必要があります。
いかにも混乱に繋がりそうな状況ですが、「こういう本はあそこにある」という形を作っておけば、上の「必要なものが必要なときにすぐとりだせるようになっている」状態を実現することも不可能ではなくなってくるはずです。
次は実践。その原則に基づいて整理するには、実用的な基準に基づいた分類が必要となります。
分類のためのヒントになったのが、
「本を、たとえば新書版とかB6判とかの判型によってそろえてならべるひとがあるが、それでは、みた目にはきれいに整頓されていても、整理されたことにはならない」という言葉でした。
確かにその通りです。同じ出版社の同じ文庫がずらりと並んだ光景がもたらす陶酔感には、言葉では言い表せないものがありますが、「必要に応じて、過去を現在によびおこすということこそ、整理ということなのである」。見た目の気持ちよさよりも、実際の必要を満たす形で本を分類することが重要なわけですね。
梅棹忠夫は、国際十進分類法ベースで本を分類していたそうです。しかし僕はそこまで物事をシステマティックに把握していないので、自分ルールに基づいて「○○したい本」「○○の本」という感じで分けることにしました。これも楽しかったです。もう一度やり直したいくらい。
親切なことに、最終的な目標も提示されていました。
それが「意識の層流状態を確保する」こと。
層流とは、水が滑らかに高速度で流れる状態のことを言うそうです。対義語である乱流が、山の渓流が岩とかにぶつかってばしゃーっとなっているあの感じのことを指しますので、その反対の状態と考えれば理解しやすいでしょう。
この目標を、僕個人に引きつけて考えてみます。
小説を書いていても、あるいは本を読んでいても、「あの本をもう一度開きたい」という瞬間がしばしば訪れます。
そうやって付き合わせることで、aとbからa+b以上の何かが生まれるのですね。
しかし探すのに手間取っていては、折角のひらめきがあっという間に色褪せてしまいます。
せっかく得た閃きを守るために、「できるだけ障害物をとりのぞいてなめらかな水路をつくることによって、」「情緒的乱流をとりのぞく」。そして「精神の層流状態を確保する」。これが目標となりました。「人間を人間らしい状態につねにおいておくために」「人間から、いかにしていらつきをへらすか」。 そういうことですね。目標を明確に策定できたぞ!
原則、実践手段、最終的な目標。ここまで揃えば、いかに僕であっても整理を成し遂げることができたのでした。
これで終わりではなく、ここから掃除機かけたりなんかかんかしたりしないといけないのですが、まあ今日はこれでいいです。本を読みます。本は片付けるものではなく読むもの
— 尼野ゆたか@5月15日コラボ小説刊行! (@amano_yutaka) October 7, 2023
部屋は外見的には汚いままです。どこからどう撮っても綺麗に写らないので、とても公開することはできません。普通だったらここで写真の一枚でも載せるところですけどね。テキストしかないぞ。
しかし、本は確かに整理されました。一度層流へと到達すれば、未整理の本に邪魔されることはなくなりました。むしろ適切な本を適切に見つけ出すことができて、更に加速した場面もしばしばあった気もします。僕みたいな知の凡人が、ここまでできるとは。
掃除で幸せになれる日が来るとは思わなかった。ありがとう「知的生産の技術」。
「創業は易く守成は難し」
物事を始めるのは簡単です。大変なのは、始めた物事を維持し発展させていくこと。
ありがたいことに、そのための手段も「知的生産の技術」には書かれていました。
それが「とりだしたら、あとはかならず、もとの位置に『もどす』」という心がけ。
拍子抜けするくらい単純ですが、しかしこれもまた真理だと思います。部屋の散らかり具合には帰還不能点が存在し、そこを超えると部屋は破綻を迎え部屋未満の何かに成り果ててしまいます。それよりも前に防衛ラインを構築し、死守するのです。
あまりに低いハードルのようですが、でもこれが難しいんですよね……。
ちなみに「出したら直す」(しまうことを近畿以西では「直す」といいます)は、尼野ゆたかが実家にいた頃からずーっと母親に言われ続けている言葉です。うちの母は……知の巨人だった……。