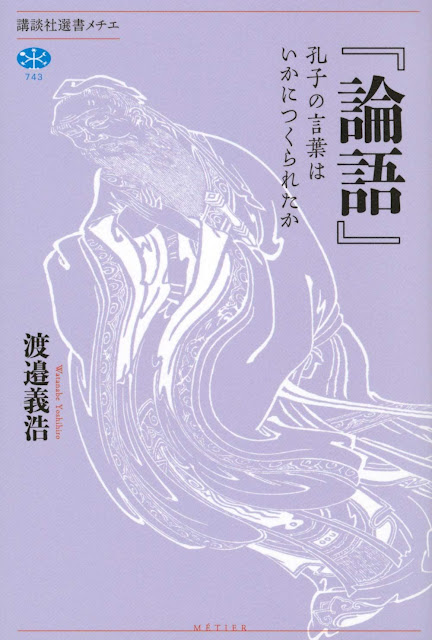渡邉義浩さん「『論語』 孔子の言葉はいかにつくられたか」(講談社選書メチエ)。
まあ常時空いていますが
【Kindleフェア】
— 講談社学術文庫&選書メチエ (@kodansha_g) April 28, 2023
本日4/28から、kindleストアにて「講談社ノンフィクション50%ポイント還元キャンペーンがはじまりました!
5/7まで10日間の開催とのことです。https://t.co/cNnqf0ptwB
講談社学術文庫や選書メチエがKindleで50%還元。定期的にあります。
どちらも単価が高めに設定されていて、迂闊にほいほい買っていたら財布と自分の胃袋に穴が空きがちですし。
僕は紙本メインなのでどうしようかな……本に書入れするの再開してから電書は大変で……
今回紹介するのは、そんな選書メチエから「『論語』 孔子の言葉はいかにつくられたか」。やや突っ込んだ内容なのですが面白いのですよ。
筆者は渡邉義浩さん。三国志では初心者向けから専門的なものまで一手に引き受け、100分De名著にも出演。あまりの寡占っぷりにそろそろ公取が研究室に踏み込んでくるのではともっぱらの噂。
早稲田大学の先生で、最近は早稲田文庫から後漢書の全訳の文庫化が始まりました。
ありがたい……汲古書院のは穴が空くどころか修善寺での夏目漱石ばりに血を吐くレベルだったから……
一冊一万円前後、全十九冊です。グハァ(見ただけで穴が空く)。
2014年に新資料が出土して一旦執筆を中断したそう
さて。本の内容です。最新の知見を取り入れつつ(中国では二十一世紀に入ってからも普通に紀元前の新史料がドカドカ発掘される)、いかにして孔子の言葉が「成立」していったかということを浮き彫りにされていきます。
保守的な思想の一つの主柱となっている感のある儒学ですが、できた当時はとてもフレキシブルに変化していた、保ち守ることとは対照的な存在であったことがよく分かります。
一般向けの本でも「この辺りは後に作られたのだろう」という話は注釈として加えられていますが、こうしてしっかり一冊の本として読めるのは大変興味深く面白い。
具体的にどう探っていくのかというと、様々な一つ一つの記述を突き合わせ、検討していくのですね。その過程は緻密にして精密で、読むのは少し大変かもですが楽しいです。理屈がカチカチと繫がる様が好きな人も楽しめるかも。
前澤正昭さん「妻と娘の唐宋時代」(東方選書)で、歴史学の面白さとして「史料を読み解く、言わば謎解きのような楽しさであり、そうしてそこから歴史像を組み立てる面白さである」「史料は人の手になるものだから、当然人間味にあふれている」とあったのを思い出しました。
歴史を素材として扱う小説には歴史を素材として小説としての面白さが溢れているわけですが、魅力の部分というのは別物であるなあというのを改めて感じます。
夏目漱石「ある場合にあっては多少の創造を許すが故に十分attractive(※アトラクティブ、魅力的)となり、attracitiveであって始めて芸術的にリアルになる。こうやったら事実に違おうか、そうしたら嘘になろうか、と戦々恐々として徒に材料たる事物の奴隷となるのは文学の事ではない」(「文章一口話」。現代表記に改めた)
前澤正昭教授「小説は作家が想像の翼を精一杯はばたかせて書き上げるものだが、歴史学は基本的に想像の世界を排除する。歴史学はあくまで史料に基づいて、ある意味では禁欲的に歴史像を追究する学問である」(「妻と娘の唐宋時代」まえがき)
硬いばかりではないのです
以前紹介した岡本隆司さん「中国の論理」(中公新書)同様、こちらも講義ノートが元だそうで。故に、論語本文にウルトラスーパー超絶解釈を施して自説に寄せる朱子(孔子より千年以上後の学者。朱子学という儒学の一派を始めた。江戸時代の日本は朱子学に強い影響を受けた)について「学力が高いのは認める」と苦笑して見せたり、ぽんこつな質問ばかりする樊遲という弟子を根気強く指導する孔子の姿に「あまり出来の良くない弟子に対して、孔子は優しい」と微笑んだりと、楽しい部分もしっかりあります。
毎回真面目にノート取ってる女子学生がふふっとなるんだろうなあ。そういうの見えると「あっあの子可愛いな」ってなっちゃいますよね。きらっきらのザ女子大生より素敵ですよね。
あれ? なんかこれ前にも言った気がするな? 気のせいかな?
その時代時代で
渡邉さんは「長い歴史の中で、思想家たちの意図のもと孔子の言動はつくられてきた」という事実を示す一方、「『論語』を読むことに意味はないのか。そうではあるまい。『論語』などの古典は、時代や個人に応じて受け取られ方が異なるからこそ、時代を超えた普遍性を持って読み継がれてきた」とも語ります。追究する学問とはまた異なる受容の仕方も提示されているのですね。
たとえばこの前井波律子さん「論語入門」(岩波新書)を取り上げましたが、あれもまた一つの(とても魅力的な)読み方だと僕は感じました。
「わたくしたちの祖父の時代までは、『論語』は少しでも学問をしようという子供たちにとって、必ず読まねばならない唯一の国定教科書だった」(貝塚茂樹「孔子」)なんてこともあれば、「その名を聞いたとき(中略)すぐさま古臭い道徳主義を連想する」「過去の封建体制と結びつけた冷たい非人間的な聖人孔子の姿を思い浮かべる」(金谷治「論語」)風潮もあったといいます。
今はどうだろう、正味お手軽な人生訓ないしビジネスマインド供給所みたいな扱いを受けていることもしばしばという気配を感じなくもないところですが、まあそれだけニュートラルに受け取られるようになったということなのでしょうか。だとしたらいいことじゃないですか~。